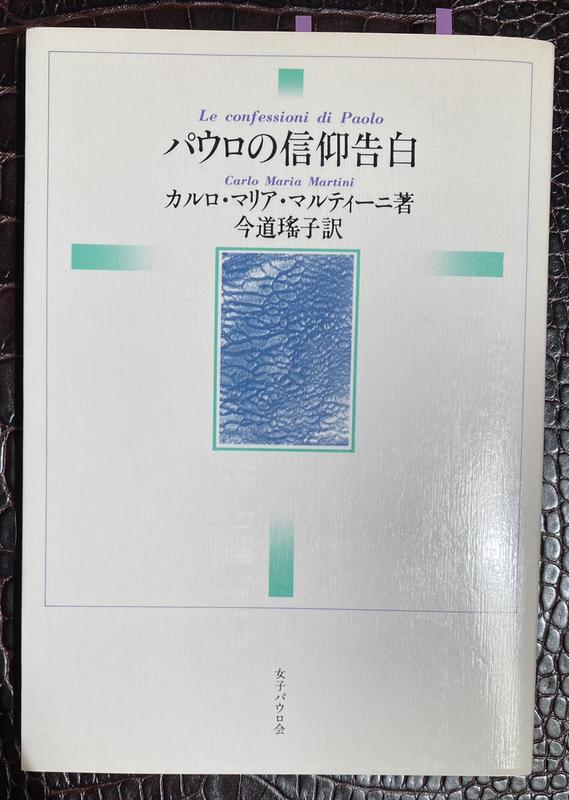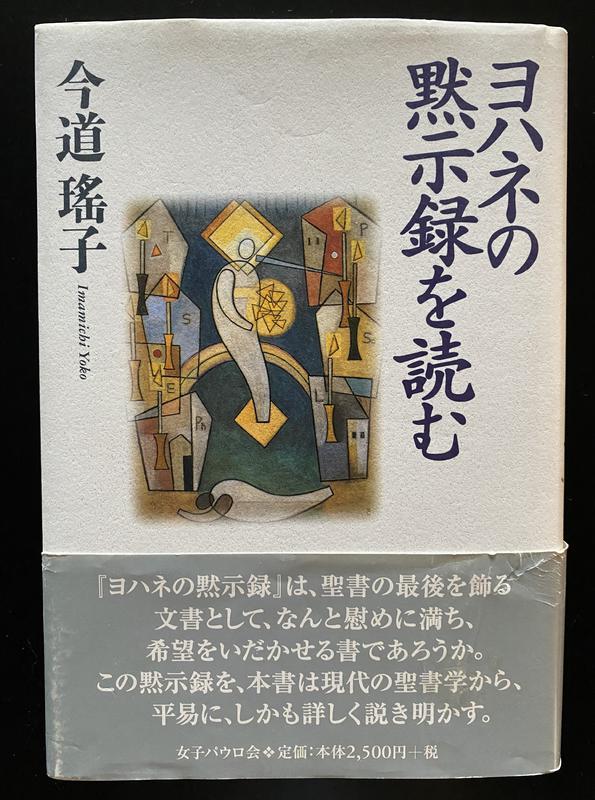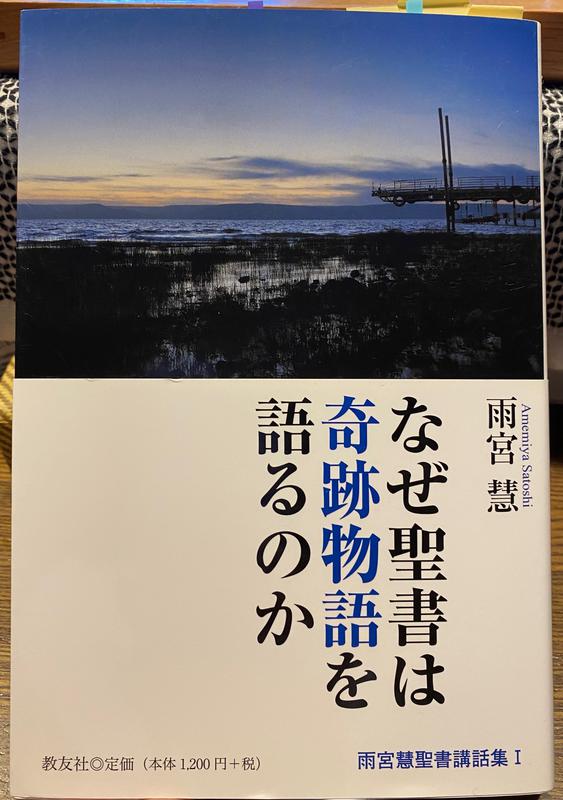カテゴリ:聖書
わたしたちは神の住まい
コロナウィルスはまだ消えたわけではありませんが、日本の各地では今年は「3年ぶり開催」のイベントやお祭りで賑わっています。
夏の帰省を断念された方もいらっしゃるでしょう。
3年ぶりに孫に会えたという方もいらっしゃるでしょう。
それぞれの楽しみ方で、今年の残暑を過ごしていきましょう!
・・・・・・・・・・・・・・・
いったいアポロとは何者ですか。
パウロとは何者ですか。
あなた方を信仰に導くために、それぞれ主がお与えになった分に応じて働いた奉仕者なのです。
わたしは植え、アポロは水をやりました。
しかし、成長させてくださったのは神です。
わたしたちは神の協力者であり、あなた方は神の畑、神の建物なのです。
(1コリント3・5~6,9)
あなた方は使徒と預言者という土台の上に、キリスト・イエスご自身を要石として築き上げられたのです。
このキリスト・イエスに結ばれることによって、建物全体は組み合わされ、主のうちにあって大きくなり、聖なる神殿となります。
キリストに結ばれることによって、あなた方も霊によってともに組み入れられ、神の住まいを築きあげることになるのです。
(エフェソ2・20~22)
主は人に捨てられましたが、神によって選ばれた尊い生きた石です。
この主に近づいて、あなた方もまた、生きた石として、霊に満たされた家に築きあげられます。
(1ペトロ2・4~5)
パウロは度々、わたしたちは神の住まいである、と例えています。
最近、この本を読みました。
パウロの人生、信仰を振り返りながら深く霊操する内容です。
パウロについて知れば知るほど、複雑な自信家、ちょっとめんどくさい頑固者だったのだろうなぁ、、、などと思ってしまいます。
ですが、彼を助けた重要な人々、バルナバ、アポロ、アキラとプリスキラなどの人々と決定的に違ったのは、頑固さゆえの根気強さと熱意でしょう。
希望と情熱に満ちた、大胆な言葉で多くの書簡を残しています。
だから、支援者の彼らと違い、イエス様への信頼に基づいた彼の教えが、こうして聖書として受け継がれてきたのではないかと思います。
パウロの遺言とも言える、使徒言行録20・18〜35でも、わたしたちが神の家であることを書き記しています。
そして今、わたしはあなた方を、神とその恵みの言葉に委ねます。
このみ言葉には、あなた方を造りあげ、全ての聖なる人々とともに受け継ぐ遺産をあなた方に与える力があるのです。
32節の「造りあげ」は、ギリシャ語で「家を建てる」に当たるそうです。
キリスト教的生活は、家を建てるのと同じく、教会と信者を次第に完成させるものだ、とフランシスコ会訳聖書の注釈にあります。
あなた方も、このように働いて、弱い人を助けなければならないこと、また、『受けるより与えるほうが幸いである』と仰せになった主イエスご自身の言葉を、心に留めておくように、わたしはいつも模範を示してきました。
35節は、自信家で熱意が溢れるパウロらしい言い方です。
『受けるより与えるほうが幸いである』とは、福音書中にイエス様の言葉として出てこない(注釈による)のですが、とても重要な教えだと思っています。
聖書の聖句の中で、いくつかわたしの人生の指針としているものがありますが、これはその一つです。
受けるより与えるほうが幸い
現実には、どうしても「こんなに与えてるのに・・・」と思ってしまうのですが、、、、、。
わたしたちが神様の住まいである、のならば、いつでも居心地良く過ごしていただけるように、心と身体を整えておくべきです。
ですから、あなた方は神に選ばれた者、聖なる者、愛されている者として、思いやりの心、親切、へりくだり、優しさ、広い心を身にまといなさい。
キリストの平和にあなた方の心を支配させなさい。
感謝の人となりなさい。
キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに宿らせなさい。
(コロサイ3・12〜15抜粋)
「了解です!」
暑い夏の盛りもあと少しです。
お身体にお気をつけになって、有意義な日々をお過ごしください。
熱い信仰
梅雨明けであって欲しい、そんな空です。
ジメジメとしているよりも、カラッと暑い季節が好きです。
以前、宮﨑神父様が「あなたの信仰がなまぬるいものでないか、自問してみてください」とお説教でおっしゃったのが、ずっと心に残っていました。
.
信仰とは火を消してしまう水ではありません。
燃え上がる炎なのです。
ストレスにさらされている人のための鎮静剤でもありません。
信仰は、神を求めて恋をしている人のラブ・ストーリーなのです!
ですから、イエスは何よりも「なまぬるいこと」を嫌われるのです。
Faith is not water that extinguishes flames, it is fire that burns; it is not a tranquilizer for people under stress, it is a love story for people in love! That is why Jesus above all else detests lukewarmness (cf. Rev 3:16).
(教皇フランシスコ Twitterより)
最近は、この本と並行してヨハネの黙示録を読んでいます。
.
黙示録は、旧約聖書の内容をベースに、独特の言い回しでさまざまなシンボルに例えて書いてあります。
わたしたち現代人にはそのシンボルを理解するのが難しく、とても難解で分かりにくい聖書の代表のように捉えてしまいます。
福音書の著者ヨハネではなく、ヨハネと言う名前の1世紀末の人物によって書かれたものだそうです。
自らを預言者であるとし、黙示録は典礼祭儀のなかで会衆に向けて朗読するための書である、と書いています。
この預言の言葉を朗読する者と、これを聞いて中に記されたことを守る者たちは、幸いだ。
時が迫っているからである。
(1・3)
会衆に向けられた書、ということで、わたしたちはもう少し気楽に読んでも良いのかもしれません。
『今おられ、かつておられ、やがて来られる方』という、黙示録独特の神様の呼び名が、1章に2回出てきます。(1・4&8)
これは、出エジプト記にある「わたしはある、わたしはあるという者だ」を分かり易くいいかえたものだ、と今道さんは書いておられます。
エジプトからの脱出、約束の地に導き、バビロン捕囚を通して民に自尊心を与え、主に忠実な民に立ち返らせてくださった神。
かつてこれほどのことをしてくださり、今わたしたちを支えてくださる神は、世界にキリスト教が広まることを通して深い意味でともにいてくださる方であり、終末にはキリストの再臨をもたらしてくださる神。
それが、『今おられ、かつておられ、やがて来られる方』なのです。
アーメンである方、忠実で信実な証人、神の創造の初めである方が、こう仰せになる、
わたしはお前の行いを知っている。
お前は冷たくもなく熱くもない。
むしろ、熱いか冷たいか、いずれかであればよいものを。
だが、このように、お前は熱くもなく冷たくもなく、生ぬるいので、わたしはお前を口から吐き出そうとしている。
(3・14~16)
『アーメンである方』という言い方も、黙示録特有のものです。
新約の中で、アーメンがキリストの属性として使われている唯一の例だそうです。
今道さんによると、わたしたちへの神の約束に対する忠実と、神の呼びかけに対する人間のポジティブな応えとしての「アーメン、はい」の両方を、一身に具現しているキリストを表すのが「アーメンである方」、ということです。
「むしろ、冷たいか熱いか、どちらかであってほしい」という表現、面白いと思います。
まるで恋人同士の会話のような、真摯な愛を求めるイエス様のみ心でしょう。
冒頭に紹介したパパ様のツイッターにある通り、信仰は、神を求めて恋をしている人のラブ・ストーリーなのです。
見よ、わたしは戸口に立ってたたいている。
もし、誰かがわたしの声を聞いて戸を開くなら、わたしはその人の所に入って、食事をともにし、その人もまたわたしとともに食事をする。
(3・20)
神様は、わたしたちが熱い気持ちで信仰を求める気持ちを期待されている、そういう感じが伝わってきます。
まだ3章までしか読み進めることができていませんが、今道さんの解説を同時に読みながら聖書をめくると、ヨハネの意図していたことが薄っすらと理解できるような気がしてきます。
わたしたちを満たすもの
「今日の聖書朗読」を読むのが習慣だという方、多いかと思います。
好きな箇所、特に旧約のお気に入りの箇所が出てくると嬉しくなり、満たされた1日を送ることができます。
.
見よ、そのとき主が通り過ぎて行かれた。
主の御前には非常に激しい風が起こり、山を裂き、岩を砕いた。
しかし、風の中に主はおられなかった。
風の後に地震が起こった。しかし、地震の中にも主はおられなかった。
地震の後に火が起こった。しかし、火の中にも主はおられなかった。
火の後に、静かにささやく声が聞こえた。
(列王記上19・11~12)
19章では、エリヤが長距離の逃避行をします。
神のことばに従って、その通りに生きてきたと自負していたエリヤは、報われないと思っていました。
そして、アハブに命を狙われ、神の山ホレブへと逃げて洞窟に引きこもります。
神が激しい風を吹かせ、地震、火を起こしても、エリヤはそこから出てきません。
「静かにささやく声」(フランシスコ会訳では「かすかにささやく声』)で、神様の現存をようやく感じ、出てくるのです。
強制的にではなく、エリヤの自由意思に任せようという神様の優しさ、エリヤへの信頼なのだ、と教わりました。
英神父様は「神はささやく声で語りかける。静けさがないと聞こえない。心の静けさを大切にして、神のささやく声を聞こう。」とおっしゃっています。
体は一つ、霊は一つです。
それは、あなたがたが、一つの希望にあずかるようにと招かれているのと同じです。
主は一人、信仰は一つ、洗礼は一つ、
すべてのものの父である神は唯一であって、すべてのものの上にあり、すべてのものを通して働き、すべてのものの内におられます。
(エフェソ4・4~6)
体、霊、希望、主、信仰、洗礼、神
この7つはそれぞれ一つであり、同時に7つの共同体でもあります。
父と子と聖霊が、それぞれ独立したものではないのと同様です。
宮﨑神父様がお説教で、こうお話しされました。
「三位一体について説明するのはとても難しい。わたし自身も完全に理解しているとは言えない。
でも、大切なのは、理解することではなく信じること。」
ともし火をともして升の下に置く者はいない。燭台の上に置く。
そうすれば、家の中のものすべてを照らすのである。
そのように、あなたがたの光を人々の前に輝かしなさい。
人々が、あなたがたの立派な行いを見て、あなたがたの天の父をあがめるようになるためである。
(マタイ5・15~16)
この箇所は、「ただで受けたのだから、ただで与えなさい。」(マタイ10・8)と同様に、わたしがとても大切に心に刻んでいる教えです。
自分のいただいている光が輝くような生き方をしたい、いつもそう思っています。
わたしたちは知っているのです、苦難は忍耐を、忍耐は練達(試練に磨かれた徳)を、練達は希望を生むということを。
希望はわたしたちを欺くことがありません。
わたしたちに与えられた聖霊によって、神の愛がわたしたちの心に注がれているからです。(神の愛がわたしたちの心の中で溢れ出ているからです。)
(ローマ5・3~5)()はフランシスコ会訳
聖書はいつも、わたしの心を満たし、生活に潤いを与えてくれます。
それが、穏やかな日常、ストレスに負けない精神の基になっていると思っています。
アウグスティヌスの「告白」の一説です。
私たちはあなたから遠ざかったり近づいたりいたします。
しかし、けっして場所ではありません。
すべての人は、自分の聞きたいことをあなたにたずねます。
しかしかならずしも、聞きたい答えを、いただくとはかぎりません。
自分の聞きたいことをあなたから聞こうとするよりもむしろ、あなたから聞くことをそのままにうけとりたいと心がける人こそは、最良のあなたのしもべなのです。
(第10巻 第26章)
人生における苦しい局面も、聞きたくないような耳の痛い言葉も、避けて通ることばかりはできません。
苦難が希望へ繋がるという教えは、生きて行く上でとても大切なものです。
最後は、今週の読書で1番心に残った文章をご紹介します。
栄光は神である御父に、また万物の王である御子に。
栄光は最高の讃美をささげるべき至聖なるお方である聖霊に。
三位一体の唯一の神は、万物を創造し、天には天に住むものを、地には地に住むものを満たされた。
神は、海と川と泉を水に住むもので満たされ、ご自分の霊であらゆるものにいのちを与え、あらゆる被造物が、智慧あるその創造主を、つまり生き続け、いつまでも永らえる唯一の原因であるお方を讃美するようにされた。
理性を備える被造物(天使および人間)は、しかし、特に、常に神を大いなる王、善き父として讃美せよ
(ナジアンゾスの聖グレゴリオス)阿部 仲麻呂神父様 訳
自分の主張
先週から、宮﨑神父様が新しいミサ式次第の解説と練習をしてくださっています。
まだ全てを理解したわけではありませんが、とても心を動かされた変更箇所があります。
主よ、あなたは神の子キリスト、永遠のいのちの糧、
あなたをおいて、だれのところに行きましょう。
これが、↓
主よ、わたしはあなたをお迎えするのにふさわしい者ではありません。
おことばをいただくだけで救われます。
これは、マタイ8章の百人隊長のことばに基づいた文で、規範版ではこちらの式文が用いられてきたようです。
すると、百人隊長は答えた。
主よ、私はあなたをわが家にお迎えできるような者ではありません。
ただ、お言葉をください。そうすれば、私の子は癒やされます。
(マタイ8・8)
ただし、これまでのとおりに唱えてもよい、となっています。
控えめな態度、言葉が美しい箇所です。
・・・・・・・・・・・・・・・
安息日に町の門を出て、祈りの場所があると思われる川岸に行った。
そして、わたしたちもそこに座って、集まっていた婦人たちに話をした。
ティアティラ市出身の紫布を商う人で、神をあがめるリディアという婦人も話を聞いていたが、主が彼女の心を開かれたので、彼女はパウロの話を注意深く聞いた。
そして、彼女も家族の者も洗礼を受けたが、そのとき、「私が主を信じる者だとお思いでしたら、どうぞ、私の家に来てお泊まりください」と言ってわたしたちを招待し、無理に承知させた。
(使徒言行録16・11~15)
この積極的な態度、面白いですね。
旧約、新約、どちらの聖書も、自分の主張をハッキリとさせるタイプの女性が多く登場します。
21世紀の現代とは違い、女性の社会的地位はとても低かったはずです。
自分の意見や意志をしっかりと持っていた女性が多くいたことよりも、そうした彼女たちの様子が聖書にイキイキと物語られていることに関心があります。
マルタとマリア姉妹のエピソードがあります。
イエス様が弟子たちとともに姉妹の家を訪問した際、食事を用意して給仕してせわしなく立ち働くマルタと、弟子たちに交じってイエス様の教えに耳を傾けるマリア。
そのことをイエス様に率直な言い方で「手伝うように、妹になんとか言ってください!」と迫るマルタ。
(ルカ10・39~42)
『マルタとマリアの家のキリスト』フェルメール作
『マルタとマリアの家のキリスト』ベラスケス作
兄のラザロが病気になったとき、人を遣わしてイエス様を呼びます。
イエス様が来られた時、マルタは迎えに行きますが、マリアは家の中に座っています。
二人とも、同じ気持ちだったのでしょう。
「ここにいてくれたら、もっと早く来てくれたら、兄は死なずに済んだのに、、、」
マルタはそれを直接ことばにして伝えますが、マリアは沈黙のうちに抗議したのかもしれません。
有名な絵画にも、意図的に「口うるさい姉」と「観想的な妹」として表現されているとおり(ベラスケスの絵は明らかにふてくされた顔の姉)、古代から西洋世界ではマリアの方が優れた人間性の持ち主だという解釈がなされていたようです。
じつはわたしも、「長女は家のために働いて、だいたい口うるさいものよ。わたしみたいに、、、。妹は気楽でいいよね~。」と思っていました。
福音宣教6月号の本多峰子さんの連載に、こう書いてあります。
「マルタはイエスを敬愛し、イエスを精いっぱいもてなそうとしていますが、同時にイエスには、全く隔てのない近さで接しています。
これはマルタが、すべての思いを包み隠さず、イエスに完全に心を開いていることの表れです。」
「ほとんどイエスをとがめるような言い方をしています。
でも同時に、イエスに行動を求め、ラザロの救いをあきらめようとはしません。
これは、マルタの信仰の強さです。
マルタはとことんイエスに食い下がります。
イエスが神に願うことは何でもかなえられると信じるマルタは、同時に、自分が心からイエスに願うことをイエスはかなえてくれると信じているのです。」
気が強く、男性にも負けずに食い下がる女性。
昔も今も、こういう女性はめんどくさいと思われるかもしれません。
「先生方、救われるためにはどうすべきでしょうか。」二人は言った。
「主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたも家族も救われます。」
そして、看守とその家の人たち全部に主の言葉を語った。
まだ真夜中であったが、看守は二人を連れて行って打ち傷を洗ってやり、自分も家族の者も皆すぐに洗礼を受けた。
この後、二人を自分の家に案内して食事を出し、神を信じる者になったことを家族ともども喜んだ。
(使徒言行録16・22~34)
真夜中なのに、洗礼を授けてもらい、家に連れて帰って食事まで。
やや強引とも思える行動です。
信仰を持つ、ということは、ときには「強引に」自分を主張してもよいのだ、とも思えます。
めんどくさいくらいに自分の主張を神様にぶつけることも、時には必要でしょう。
リディアのように積極的で、マルタのように意志が強く、妹のマリアのように秘めた強さを持ち、
「はいはい、わかりました」
そう神様に言われるくらいまで、強い信仰を貫いて生きて行ってもいいのです。

奇跡物語が語るもの
中庭の春の装いが、小雪の舞うなかとても美しい日曜日でした。
宮﨑神父様のお説教にとても心を打たれました。
「ウクライナのために祈っていますか?」と問われ、気になってはいるものの、それは「戦争が始まるかも」というニュースとしてに過ぎなかった自分が恥ずかしくなりました。
遠い国のニュースではなく、隣人が戦争と隣り合わせの現実に直面していることを忘れずに、みなさん祈りましょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・
マタイ、マルコ、ルカの3つの共観福音書には、同じ出来事や教えが書かれている箇所があります。
福音書を読んでいると、注釈でその並行箇所が示されているので、同じ話を他の2人も書いていることを知ることが出来ます。
全く同じエピソードが、福音記者によっては詳しく書かれていたり、短かったり、時には全く違った趣旨で書かれていることがあります。
話の大筋はだいたい同じなのですが、当然3人にはそれぞれに伝えたいポイントがあって、よく読むとわたしたちに訴えていることが違うことが分かります。
エリコの盲人、バルテマイが癒される奇跡物語があります。
(その道の)道端に座っていたバルテマイという盲目の物乞いが、何度黙らせようとされても「ダビデの子イエスさま、わたくしをあわれんでください」と叫び続けます。
イエスが「何をわたしにしてもらいたいのか」とお尋ねになると、盲人は、「先生、見えるようにしてください」と言った。
そこでイエスは仰せになった。
「行きなさい。あなたの信仰があなたを救った」。
するとたちまち、盲目の人は見えるようになり、(その道を)イエスに従った。
(マルコ10・46~52)
イエスは立ちどまり、彼らを呼んで、「何をしてもらいたいのか」とお尋ねになった。
二人は「主よ、わたくしたちの目を開けてください」と言った。
イエスは哀れに思い、その目に手をお触れになると、彼らはすぐに見えるようになった。
そして、イエスについて行った。
(マタイ20・29~34)
そこで、イエスが「見えるようになれ。あなたの信仰があなたを救った」と仰せになった。
すると、盲人はたちどころに見えるようになり、神をほめたたえながら、イエスについて行った。
これをみて、民は皆、神を賛美した。
(ルカ18・35~43)
3人の福音記者たちの意図はそれぞれ違うところにある、と雨宮神父様の本にあります。
マルコ
■「見えるようにしてください」と、物事を見抜く視力の回復が願われている。
■(その道の)という言葉が本来のギリシャ語原文には書かれていて、エルサレムに向かう途上で盲人に会っている。
■奇跡そのものよりも、イエスに叫んだ者が十字架への道=苦難を通って救いへと至る道に招き込まれたことを表現。
■わたしたち読者にも、どうすればイエスによる救いの道へ入れるのかを教えている。
マタイ
■「目を開けてください」と、ごく実質的な願いがなされている。
■盲人の目が開かれた、という奇跡物語を語ることに主眼がある。
ルカ
■奇跡を通して働く神の力への賛美。
■イエスが神として顕現し、叫び求める者に救いを与えるという教え。
『なぜ聖書は奇跡物語を語るのか』
雨宮 慧 神父 著より
ひとりで聖書を開いても、ここまで深く意図を読み取ることはできません。
この本を読んで、まさにわたしも「目が開かれた」気持ちです。
聖書は、歴史的な出来事を客観的に書いている本ではない、ということはご存じのとおりです。
聖書を書いた人々が伝えたかったのは、その出来事の背後にひそんでいた意味なのだ、と雨宮神父様が書いておられます。
「そして、聖書が出来事を叙述するとき、詩や戯曲の表現方法を駆使し、シンボルや詩的表現を使って把握した意味を伝えようとしています。
イメージを限りなく広げる言葉が好まれるのです。読むほうもそのつもりで読む必要があります。」
歴史書は出来事を正確に客観的に叙述して真理を追求するに対して、新約聖書は復活体験が根本になって、知りえた真理からさかのぼって出来事をとらえているのです。
イエス様が行われた奇跡に立ち会った弟子たちでさえ、その時にはその本来の意味を理解できていなかったのす。
復活体験によってイエス様の神性を知り、宣教活動を通してその真理を理解した彼らは、そのことを以前の出来事のなかに確認しながら書き記したのです。
ですから当然、一つの奇跡物語にいくつもの強調したい真理がうまれるわけです。
聖書を読む時にこのことを分かっていて読むかどうかで、心に訴えてくることが変わるはずです。
このことを踏まえたうえで以下の箇所を読んでみてください。
わたしは、以前とは違う景色が見えた気がしました。
「まだ、分からないのか。悟らないのか。心がかたくなになっているのか。目があっても見えないのか。耳があっても聞こえないのか。
覚えていないのか。わたしが五千人に五つのパンを裂いたとき、集めたパンの屑でいっぱいになった籠は、幾つあったか。」弟子たちは、「十二です」と言った。「七つのパンを四千人に裂いたときには、集めたパンの屑でいっぱいになった籠は、幾つあったか。」「七つです」と言うと、イエスは、「まだ悟らないのか」と言われた。
(マルコ8・14~21)